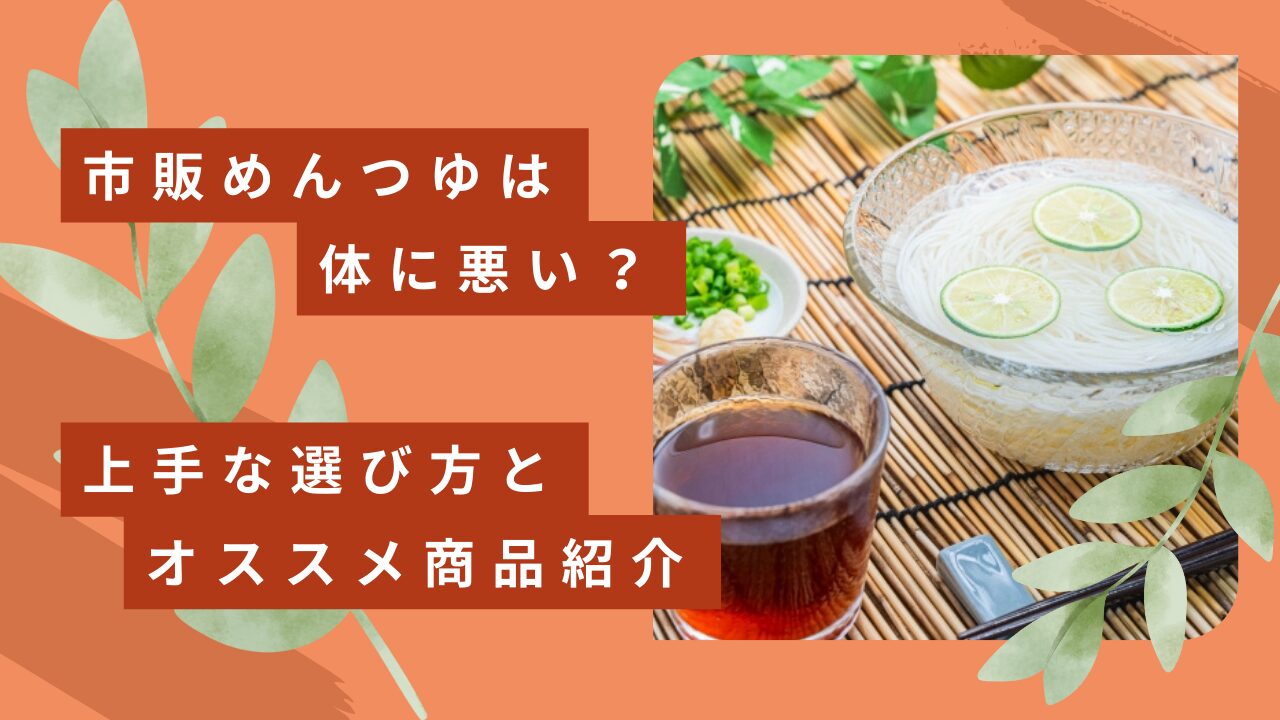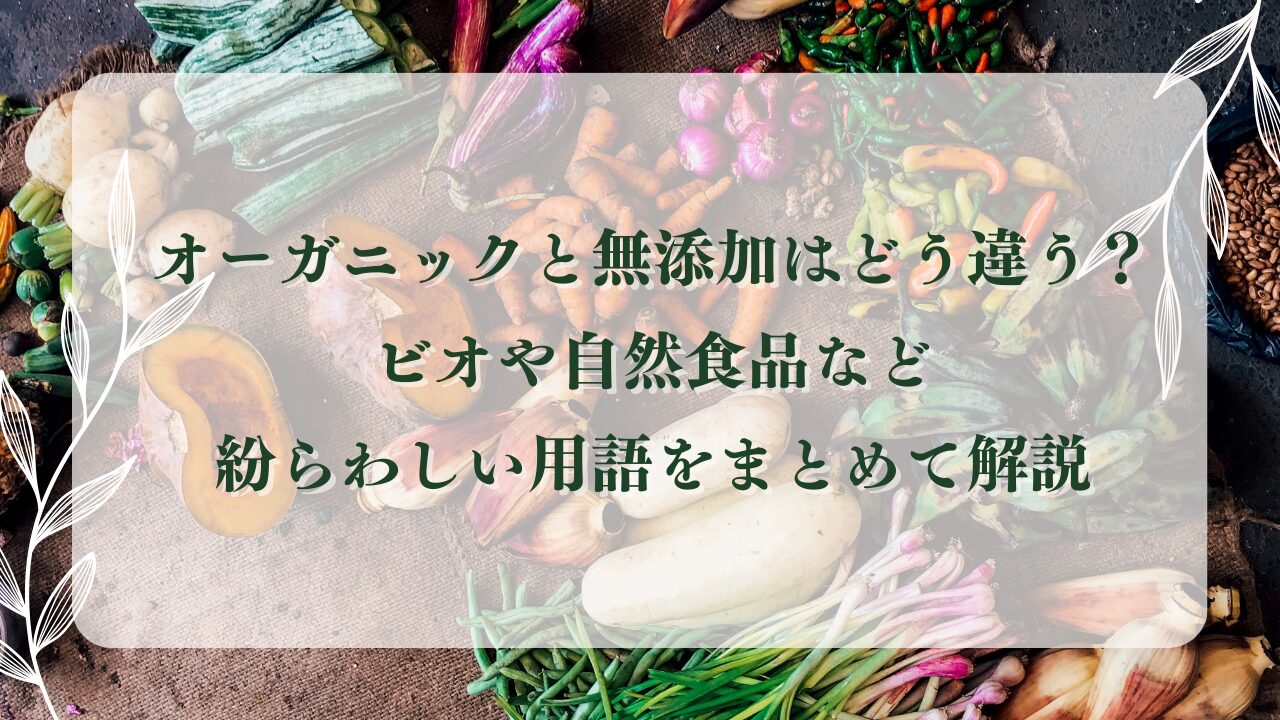有機栽培・自然農法・ビオディナミとは?環境配慮型農業の違いと特徴
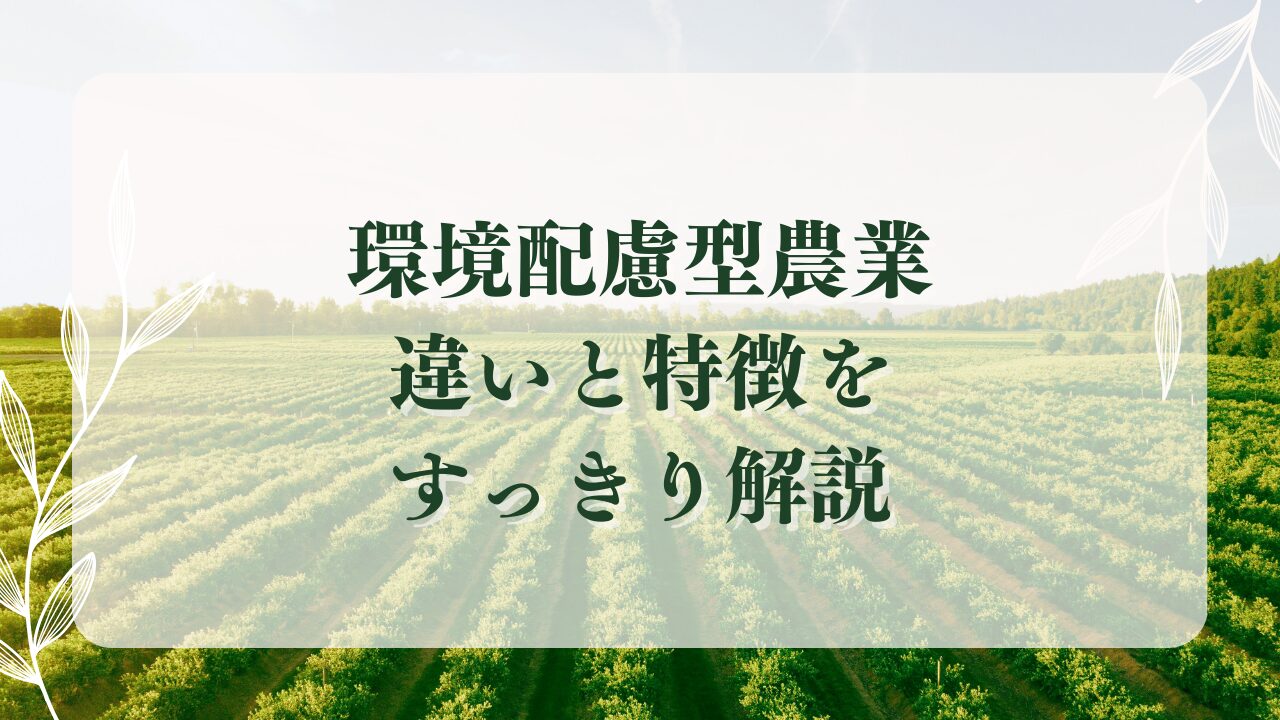
この記事では:
有機栽培と自然農法はどう違う?
サステナブル・ビオディナミ・リジェネラティブなど徹底解説します!
はじめに

「有機栽培」「自然農法」「ビオディナミ」など、環境配慮型の農法が注目されている背景
「有機栽培」「自然農法」「ビオディナミ」といった環境配慮型の農法が注目されている背景には、環境問題への意識の高まりや食の安全志向、さらには気候変動や化学肥料の高騰といった現実的な課題があります。
長期的な化学肥料や農薬の使用による環境汚染や生態系への影響が懸念されるなか、土壌や水質の保全、生物多様性の維持といった観点から、環境にやさしい農法は支持を集めています。
加えて、異常気象や国際的な食料供給の不安定化により、化石燃料や化学資材への依存を減らす“持続可能な農業”への関心も一層強まっています。食品の安全性を重視する消費者意識も後押しし、「安心できる食材」への需要が増え続けています。
実は最近のトレンドではない
こうした農法は、決して最近になって生まれた新しいトレンドではありません。それぞれの農法が提唱され始めたきっかけと背景を見ていきましょう。
有機栽培の始まりと広まり
有機栽培は20世紀初頭、ヨーロッパで提唱され始めました。当時は急激な近代化が進み、化学肥料や農薬の開発・大量使用による環境や健康への弊害が懸念されていました。日本では高度経済成長の反動として公害問題が深刻化し、1970年代の環境運動とともに有機農業が広まっていきました。
日本で自然農法が生まれた背景
自然農法は1930年代に岡田茂吉が「自然の力を最大限に活かす」思想を基盤として提唱しました。産業化の波が押し寄せ、自然や農村が軽視されるようになっていた時代にあって、自然界の循環に学び、人間の介入を最小限にして作物を育てる方法に目を向けたのです。
ビオディナミ農法の誕生
ビオディナミ農法は1924年、ルドルフ・シュタイナーが提唱したのが始まりです。化学肥料の普及による「土壌の生命力低下」への危機感がきっかけとなり、農場全体をひとつの生命体と捉える独自の哲学を持つ体系的農法として発展しました。
人類と農業の長い歴史の中で
人類と農業の長い歴史の中で、環境や食べ物に科学的なものが加わり始めたのはごく最近のことです。健全な環境や健康への不安と危機感は、昔から変わらず抱かれてきた感情なのですね。
我々消費者との関わり

少し難しい話が続きましたが、結局のところ、私たちがこうした農法に関心を持つのは、難しい理屈よりも「安心して食べたい」「できれば体や環境にやさしい方がいい」という、普段の生活の中での自然な気持ちからです。
「おいしくて安心できるものを選びたい」という日常の気持ち、その小さな選択が、自分の暮らしを心地よくし、未来の環境も支えていくのです。
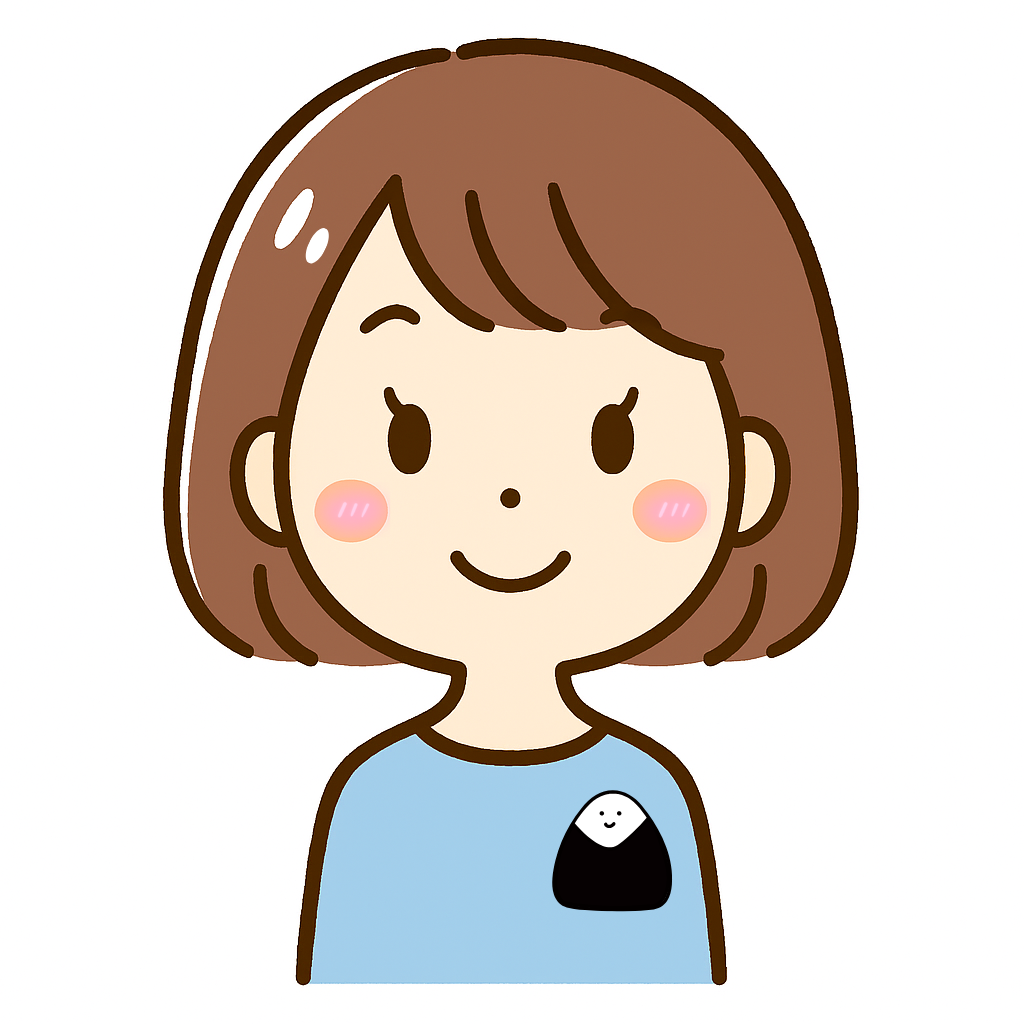
身体の健康だけでなく心の健康と豊かさにつながることも大切です。自分にとって良い塩梅で賢く取り入れていきたいですね!
有機栽培(オーガニック)
有機栽培(オーガニック)をすっきりまとめ!
有機栽培(オーガニック)の定義
- 化学合成肥料・農薬不使用
化学肥料や農薬を一切使わず(2年以上使用不可の土壌)、堆肥や緑肥など自然由来の資材で土作りと病害虫対策を行います。 - 遺伝子組み換え技術不使用
遺伝子組み換え作物やその資材は認められていません。 - 認証制度
日本の場合は「有機JAS規格」により明確な基準・検査制度が設けられ、認証に合格したものだけが「有機」「オーガニック」の表示をできます。
有機栽培(オーガニック)の目的
有機栽培(オーガニック)の目的は、自然の力を活かしながら環境への負荷を減らし、持続可能な農業を実現することです。
農林水産省の定義では、化学合成された肥料や農薬を使わず、堆肥・緑肥・微生物など自然界の働きを取り入れて、土壌や生態系の健康を保つことが基本とされています。
その目的は大きく次の4つに整理できます。
- 自然の循環機能を守る
土壌や生態系の健全さを維持し、自然の生産力を引き出す。 - 環境保全と生物多様性の向上
水質保全や土壌流出の防止など、環境全体のバランスを保つ。 - 安全で安心な食の提供
合成農薬や化学肥料を使わず、消費者に信頼できる農産物を届ける。 - 持続可能な農業の推進
資源循環や地域性を重視し、長期的に続けられる農業体系をつくる。
つまり、有機栽培の公式な目的は「自然の循環を生かし、環境と人々の安心を守りながら、持続可能な農業を確立すること」だと言えます。
有機栽培(オーガニック)の認証制度
世界のオーガニック認証制度
世界各国にオーガニックの認証が存在します。
- 日本:有機JAS認証
- アメリカ:USDAオーガニック(NOP)認証
- EU:EUオーガニック認証
- フランス:ECOCERT認証
日本の有機JAS認証は、国際食品規格「コーデックスガイドライン(FAO/WHO)」を参考に定められています。
また、アメリカ・EU・カナダなど主要国とは「同等性協定」により相互に認証を認める仕組みがあり、日本の有機JAS認証品を「Organic」と表示して輸出できる場合もあります。
ただし、世界共通の認証制度は存在せず、各国ごとに認証取得が義務づけられている点には注意が必要です。
日本に輸入される有機食品も、国内で流通させるためには必ず「有機JAS認証」を取得しなければ「有機」「オーガニック」と表示できません。
日本の有機JAS認証制度
<概要>
日本では、農林水産省が定める「有機JAS認証制度」に基づき、登録認証機関の検査を受けて認証を取得したものだけが「有機」「オーガニック」と表示できます。
認証を受けた商品には 有機JASマーク が貼付され、未認証の商品にオーガニック表示をすることは法律で禁じられています。
<認証を受けるための条件>
- 化学合成肥料・農薬の不使用
(農地は播種または植付け前2年以上、多年生作物では収穫前3年以上の不使用が必要) - 遺伝子組換え技術の不使用
- 周辺からの禁止資材の流入防止(防風ネットや緩衝帯の設置など)
- 採取場でも自然の生態系を維持する方法で収穫すること
- 原材料の95%以上が有機原料(水・塩を除く)
- 化学的な添加物・薬剤の使用制限
- 残留農薬や異物混入への配慮
※有機JAS認証ワンポイント
- 年1回の定期調査と継続認証の更新手続きが必要です
- 化粧品・繊維など、一部の分野には有機JASの基準が存在しません
(したがって、化粧品に「オーガニック」と表示されているものの多くは、メーカー独自の基準やキャッチコピーによるものです。
プラスone:有機栽培と「無農薬」「特別栽培」の違い
有機栽培は上記よりも厳格な基準と国際的な認証が求められます。
自然農法
自然農法をすっきりまとめ!
自然農法の定義
- 化学肥料・農薬を使わない
農薬や化学肥料を用いず、自然界の摂理や生態系のバランスを尊重する農法です。 - 耕作・除草も最小限
田畑を耕さない、不必要な除草をしないなど、人為的な介入をできるだけ減らすことが特徴です。 - 創始者
岡田茂吉(1882〜1955)と福岡正信(1913〜2008)が提唱。岡田は自然界の循環を模した農法を提唱し、福岡は「不耕起・不除草・不施肥・無農薬」を柱とする自然農法を広めました。
自然農法の目的
自然農法の理念は「大自然の摂理を尊重し、生きている土の力を最大限に生かすこと」です。目的は次のように整理できます。
- 自然との共生
生態系を壊さず、自然界のバランスを保ちながら農業を営む。 - 土壌の健康維持
微生物や自然の働きを活かし、化学物質に頼らず土壌を健全に保つ。 - 安全な作物の生産
化学肥料・農薬を使わないことで、安心できる作物を育てる。 - 持続可能な農業
資源を循環させ、長期的に続けられる農業体系を目指す。
自然農法の認証制度
- 公的な統一認証は存在しない
日本には「有機JAS」のような政府公認の自然農法専用認証はありません。 - 独自認証の事例
一部の団体(例:公益財団法人 自然農法国際研究開発センター/INFRC)が独自に認証を行っていますが、法的拘束力はありません。 - 有機JASとの違い
有機JASは国が定める基準と制度があるのに対し、自然農法は統一基準がなく、実践者ごとに考え方や方法に幅があります。
プラスone:有機農法や慣行農法との違い
| 農法種類 | 農薬使用 | 化学肥料使用 | 耕起 | 除草 | 基準・認証 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自然農法 | 不使用 | 不使用 | しないことが多い | しないことが多い | 公的統一基準なし |
| 有機農法 | 天然由来農薬は可 | 有機肥料は使用可 | 行うことが多い | 行うことが多い | 有機JAS認証あり |
| 慣行農法 | 化学農薬使用 | 化学肥料使用 | 行う | 行う | 公的基準あり |
ビオディナミ農法(バイオダイナミック農法)
ビオディナミ農法をすっきりまとめ!
ビオディナミ農法の定義
- 起源
1924年、ドイツの哲学者ルドルフ・シュタイナーが提唱した有機農法の一種。 - 基本概念
農場全体を「ひとつの生命体」として捉え、土壌・植物・動物・人間が一体となる循環型農業。 - 特徴
化学肥料や農薬を使わず、ハーブ・鉱物・家畜由来の「調合剤」を土壌に施す。
太陽・月・惑星の動きに合わせた農事暦に従って作業を行う。 - 思想的側面
単なる農法にとどまらず、宇宙や自然との調和を重視する思想・哲学的側面も持つ。
ビオディナミ農法の目的
- 土壌の健康と生命力の向上
自然の力を引き出し、化学資材に頼らず生態系を豊かに保つ。 - 循環型の自給自足的農場づくり
堆肥や種子、家畜などを農場内で循環させ、外部資源への依存を減らす。 - 宇宙と自然のリズムに調和
天体の動きに沿った農作業を行い、持続可能で生命力あふれる農業を実現する。
ビオディナミ農法の認証制度
世界の認証制度
- 代表的認証:ドイツ発祥の Demeter International(デメター認証)
世界で最も厳格かつ広く認知されるビオディナミ認証です。 - 基準の特徴
- 農場全体が循環型システムであること
- 化学肥料・農薬の不使用
- シュタイナー由来の調合剤の使用
- 農事暦に基づく作業スケジュールの遵守
- 土壌・生態系保全への取り組み - その他の認証
米国のBD認証など地域ごとの制度もありますが、Demeterが国際標準とされています。
日本の状況
- 日本にもビオディナミ農法を実践する農場がありますが、ビオディナミ専用の公的認証はありません。有機JAS認証と併用されるケースが多いです。
- 日本でも、基本的にはDemeter国際認証に依拠しています。
プラスone:オーガニックとの違い
- オーガニック:化学資材を排除し、環境への負荷を減らすことに重点。
- ビオディナミ:オーガニックの要件を満たしつつ、さらに 宇宙や自然界のリズムとの調和 を重視する点で独自性がある。
サステナブル農法(持続可能な農業)
サステナブル農法をすっきりまとめ!
サステナブル農法の定義
- 概要
サステナブル農法は、環境保全・資源の持続的利用・社会的公正を考慮しながら、次世代に農業資源を継承することを目指す農業手法全般を指します。 - 特徴
化学肥料や農薬の使用抑制、土壌の健康維持、生物多様性の保全、水資源の節約、農業者や地域社会の福祉への配慮など、多面的な取り組みを含みます。
サステナブル農法の目的
- 環境負荷の低減
土壌や水質の汚染を避け、生態系を守る。 - 資源の効率的活用
肥料・水・エネルギーを無駄なく利用する。 - 経済的な持続可能性
農家の収益安定や地域経済の活性化を支える。 - 社会的公正
労働環境の改善や消費者の健康保護に配慮する。 - 次世代への資源継承
未来の世代にも持続可能な農業環境を残す。
サステナブル農法の認証制度
日本の認証制度
- 日本には「サステナブル農法専用の国家認証制度」は存在しません。
- 実際には 有機JAS認証 や「環境保全型農業」の枠組みがサステナブルの要素を担っています。
- 有機JASでは、農薬・化学肥料の不使用や圃場管理、記録の徹底などが基準とされ、認証取得後も年次検査による継続適合が求められます。
世界の認証制度
- Rainforest Alliance や GlobalG.A.P.(グローバルGAP) など、国際的に広く普及した認証制度があります。
- 認証要件には、土壌保全・水資源管理・農薬使用の制限・労働者の権利保護などが含まれ、環境と社会の両面を包括的にチェックします。
プラスone:サステナブルとSDGsの違い
- サステナブル:理念そのもの。社会・環境・経済を将来にわたって持続させるあり方。
- SDGs:国連が定めた具体的な国際目標(17のゴール、169のターゲット/2030年まで)。
サステナブルは「考え方」、SDGsは「達成すべき指標」としての位置づけです。
リジェネラティブ農業(再生型農業)
リジェネラティブ農業をすっきりまとめ!
リジェネラティブ農業の定義
リジェネラティブ農業は「環境再生型農業」とも呼ばれ、土壌や自然環境を守るだけでなく再生・回復させることを目的にした新しい農業です。
不耕起栽培やカバークロップ(被覆作物)、輪作などを取り入れ、土の力や生物多様性を高め、気候変動対策としても注目されています。
リジェネラティブ農業の目的
- 土壌や生態系を再生し、健康な状態に戻す
- 土に炭素を貯め、温暖化防止に貢献する
- 長く続けられる持続可能な農業をつくる
リジェネラティブ農業の認証制度
国際的な統一認証はまだありませんが、アメリカ発の ROC(Regenerative Organic Certification) などがあり、土壌の再生や社会的公正などを重視しています。
日本では専用制度はなく、有機JASや環境配慮型農業が近い役割を果たしています。
まとめ
リジェネラティブ農業は「自然を再生する」ことを目的にした農法で、土や環境を元気にしながら持続可能な農業を目指す動きです。
減農薬栽培(低農薬栽培)
減農薬栽培をすっきりまとめ!
減農薬栽培の定義
減農薬栽培は、通常の栽培より農薬の使用を大きく減らす農法です。
日本では「特別栽培農産物」の基準に基づき、農薬や化学肥料を慣行の半分以下に抑えたものが対象となります。
減農薬栽培の目的
- 農薬による環境や健康への影響を減らす
- 将来も続けられる農業に近づける
- 消費者に安心感を与える
減農薬栽培の認証制度
- 日本:農林水産省の「特別栽培農産物ガイドライン」に基づき表示可能。都道府県ごとに独自認証もあり。
- 世界:減農薬だけを対象とした国際認証はなく、主に有機やGlobalG.A.P.の中で評価されます。
まとめ
減農薬栽培は「農薬をゼロにする」のではなく「半分以下に減らす」取り組みです。有機栽培ほど厳格ではありませんが、環境や健康に配慮した農法として普及しています。
各農法の比較表
| 農法 | 定義・特徴 | 目的 | 認証制度 |
|---|---|---|---|
| 有機栽培(オーガニック) | 化学肥料・農薬を使わず、堆肥や緑肥を活用。遺伝子組換え禁止。 | 環境負荷を減らし、持続可能で安心できる食を提供。 | 日本は有機JAS認証。海外はUSDA(米国)、EUオーガニックなど。 |
| 自然農法 | 農薬・肥料を使わず、耕起・除草も最小限。自然に委ねる農法。 | 自然との共生・土壌の生命力尊重。 | 公的な統一制度はなし。団体による独自認証(例:INFRC)。 |
| ビオディナミ農法 | 1924年にシュタイナーが提唱。農場を生命体とみなし、天体のリズムや調合剤を用いる。 | 土壌と作物の生命力向上、自然・宇宙との調和。 | Demeter認証(国際的基準)。日本では有機JASと併用も。 |
| サステナブル農業 | 環境・経済・社会の持続可能性を重視する農法全般。 | 環境保全、資源効率化、農家の安定、社会的公正。 | 日本では専用制度なし。有機JASや環境配慮型農業が該当。海外ではRainforest Alliance、GlobalG.A.P. など。 |
| リジェネラティブ農業 | 土壌や自然環境を守るだけでなく再生・回復する農法。 | 土壌の再生、炭素隔離、生態系回復、農業の持続性。 | 国際的に**ROC(Regenerative Organic Certification)**など。日本は専用制度なし。 |
| 減農薬栽培 | 慣行農法より農薬を大幅に減らす。日本では農薬・化学肥料を慣行の50%以下に制限。 | 環境や健康リスクを減らし、消費者に安心感を与える。 | 日本は「特別栽培農産物ガイドライン」。世界統一制度はなし。 |
最後に…
「オーガニック」「自然農法」「ビオディナミ」「サステナブル」「リジェネラティブ」「減農薬」――
似ているようで、それぞれ目指す方向性や強調点が異なる農法です。
大切なのは、どの農法が一番良いかを決めることではなく、それぞれの特徴を理解して「自分が暮らしに取り入れたい価値観やスタイル」を選ぶことです。良さを競うものや、個人レベルでは誰かにアピールするものでもありません。
肩ひじを張らずに、自分や家族にとって心地よい食と環境のあり方を見つけていくことが、豊かな生活につながります。